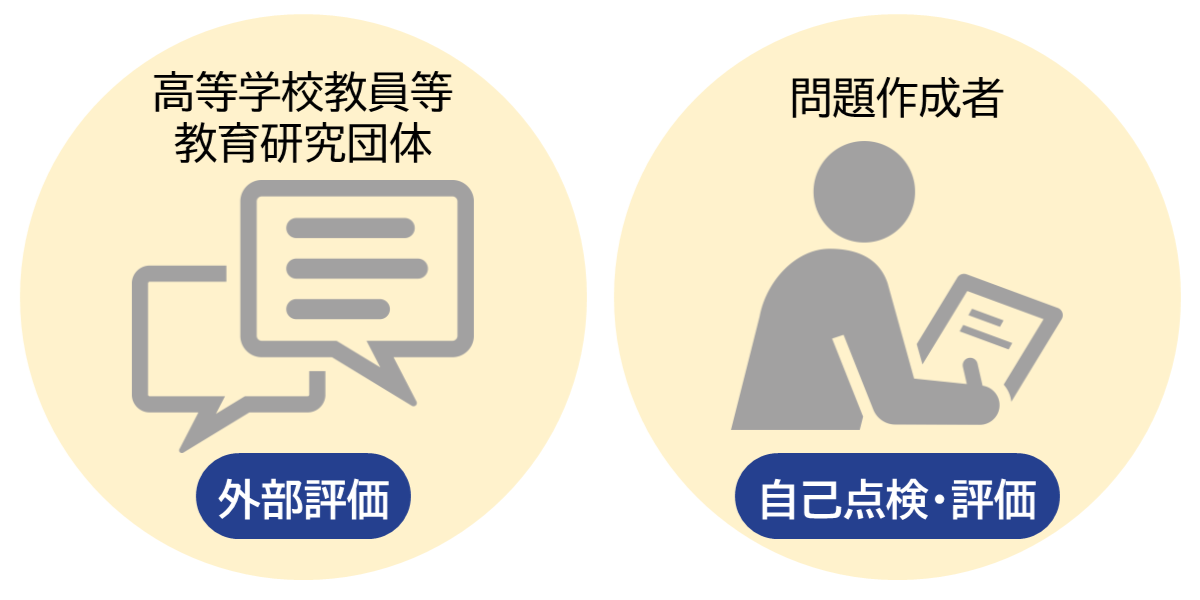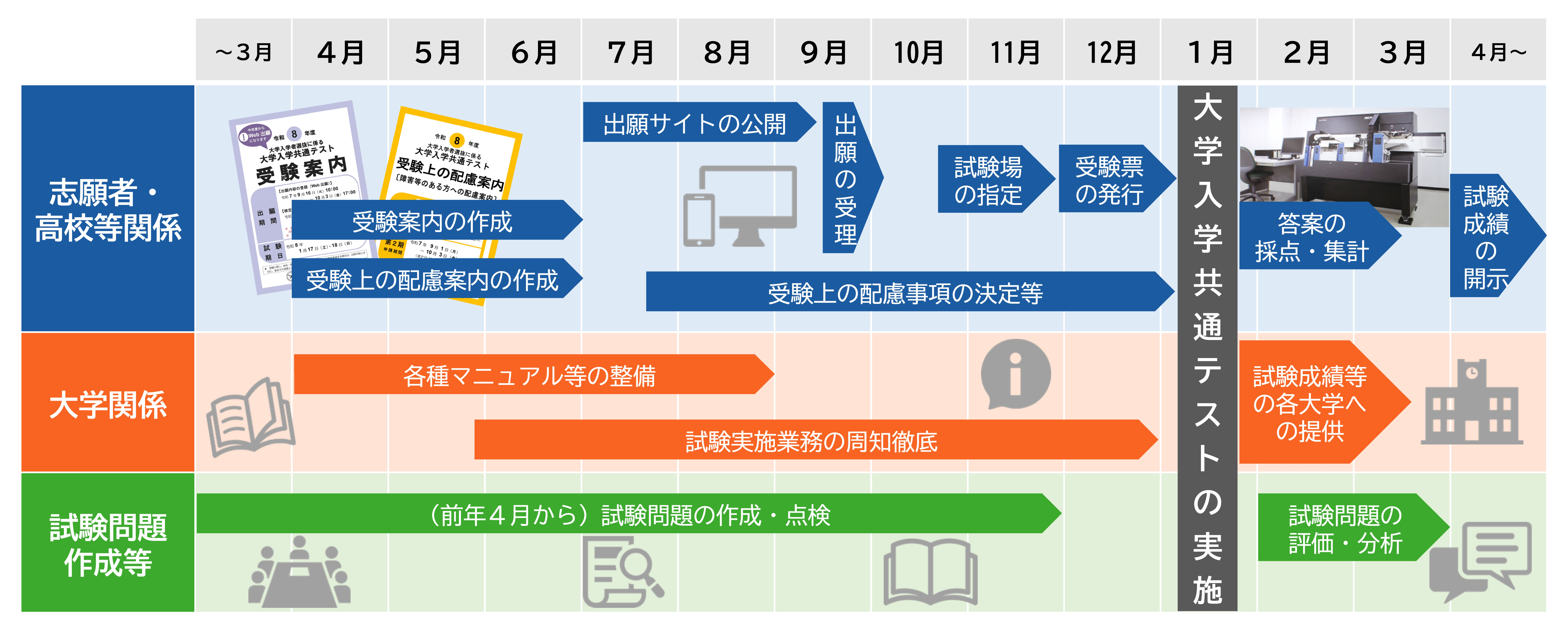- 大学入試センター
- 大学入学共通テスト
- 大学入学共通テストの概要
- 大学入学共通テストの業務と実施経費
大学入学共通テストの業務と実施経費
大学入試センター(以下、本ページでは「センター」といいます。)は、大学が共同して実施する試験である大学入学共通テスト(以下、本ページでは「共通テスト」といいます。)に関し、「一括して処理することが適当な業務」を行っています。
本ページでは、共通テストの実施に際し、センターが行っている業務や、これに必要な経費等について紹介します。
本ページでは、共通テストの実施に際し、センターが行っている業務や、これに必要な経費等について紹介します。
大学入試センターの収支
収入・支出の大半を共通テスト実施関連の項目が占めています。
センターの収入
- グラフは、センターの1年間の収入の内訳を示しています。
- 志願者からいただいている検定料・成績閲覧手数料、受験者の成績を大学に提供する際に大学からいただいている成績提供手数料でセンターの収入の約96%を占めています。
- センターは、平成23年度以降、国から運営費交付金(※)が措置されていません。
(※)運営費交付金とは、政府が予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために交付する資金のことです。
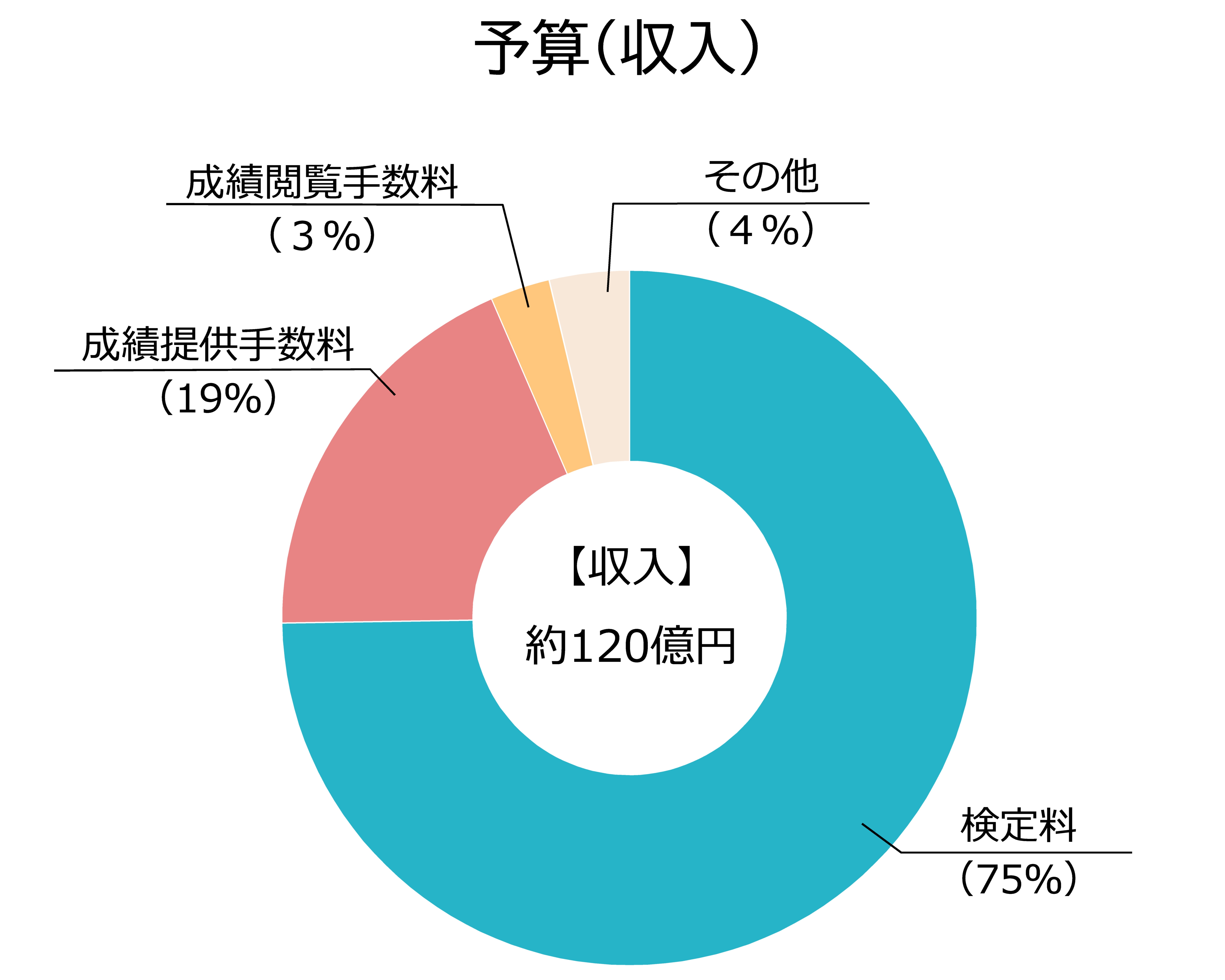 クリックするとPDFファイルが開きます(25.4 KB)※小数点以下を四捨五入しているため、合計は100%となりません。
クリックするとPDFファイルが開きます(25.4 KB)※小数点以下を四捨五入しているため、合計は100%となりません。センターの支出
- グラフは、センターの1年間の支出の内訳を示しています。
- センターの支出のうち約85%を占める試験実施経費は、共通テストの実施業務と関連した直接的な経費であり、狭義のものです。このほか試験実施業務に関連する人件費等については別途計上しています。
- センターは、共通テストの実施のほか、大学の入学者選抜方法の改善に関する調査研究、大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供業務を行っています。これら業務に関する支出には、それぞれ入学者選抜方法改善研究経費、大学入学共通テスト等情報提供経費が充てられています。
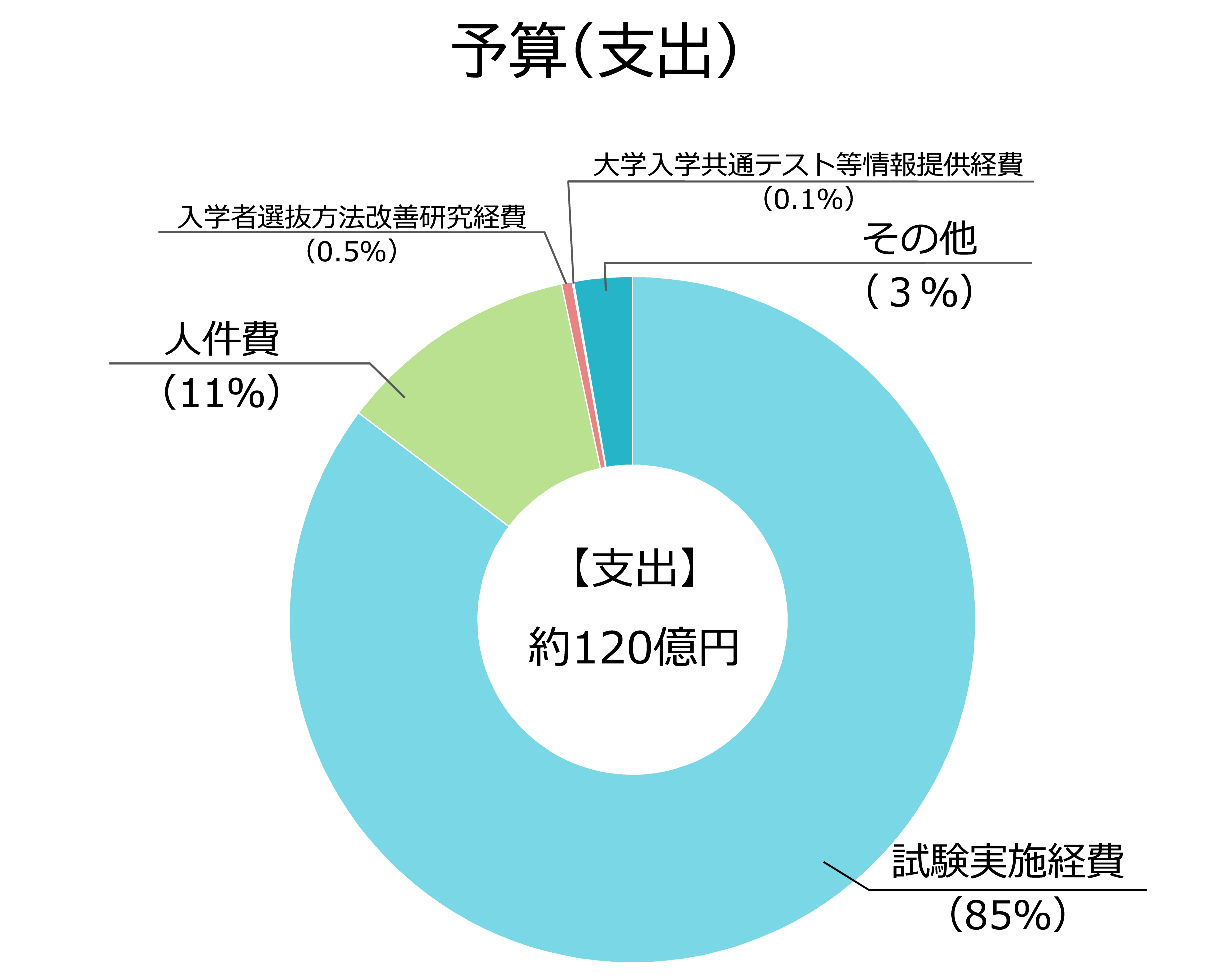 クリックするとPDFファイルが開きます(34.7 KB)※小数点以下を四捨五入しているため、合計は100%となりません。
クリックするとPDFファイルが開きます(34.7 KB)※小数点以下を四捨五入しているため、合計は100%となりません。試験実施経費(狭義)の内訳と関連する業務
共通テストの実施に関する多様な業務に充てられるのが試験実施経費です。
支出のうち、大半を占める試験実施経費の内訳を下の表で示しています。
| 試験実施経費の内訳 | 関連する業務(ページ内リンク) |
|---|---|
| 試験問題に関する経費(人件費を除く) | |
| 大学に配分する試験会場運営費等 | |
| 志願者、受験者、大学に関するセンター業務の経費(大学に配分する試験会場運営費等及び人件費を除く) | |
| その他の経費(人件費を除く) |
共通テストに関する業務の流れと全体像
共通テスト実施前
共通テスト実施当日
共通テスト実施後
共通テスト実施前の業務(実施に向けた準備、問題の作成など)
共通テストの企画・立案
大学・高等学校等関係者などで組織する委員会、部会等で審議しています。
- 共通テストの企画・立案に関して調査審議するため、国公私立大学関係者や高等学校関係者等で組織する「大学入学共通テスト企画委員会」をはじめとする各種委員会等を置いています。
- 後述する「受験案内」「受験上の配慮案内」や試験実施に関する各種マニュアル等の内容もこれらの委員会等で審議しています。
共通テストの企画・立案に関する主な委員会、部会
| 会議体の名称 | 具体的な審議事項 |
|---|---|
| 大学入学共通テスト企画委員会 | 以下の主な事項の基本方針の策定及びその他の重要事項について調査審議する。
|
| 実施方法部会 | 実施方法及び情報処理に関し、基本方針案の策定、企画・立案に関する事項を調査審議する。 |
| 配慮事項部会 | 障害等のある志願者に対する受験上の配慮に関し、基本方針案の策定、企画・立案に関する事項を調査審議する。 |
| 問題作成部会 | 共通テストの問題作成に係る基本方針案の策定及び共通テストの問題作成等を行う。 |
受験案内の作成
共通テストの「受験案内」を作成しています。
受験案内の作成
- 志願者及び高等学校等関係者が、共通テストの出願手続きや試験の制度について十分に理解した上で、出願手続きを円滑に行うことができるよう、必要な事項をまとめた受験案内を作成しています。
- 受験案内は、例年6月下旬頃にウェブサイトに公開します。また、7月上旬頃に公開する共通テスト出願サイトからもダウンロードできます。
 受験案内の表紙
受験案内の表紙(令和8年度共通テスト)
高等学校等関係者への周知
- 高等学校等関係者には、志願者が間違いなく出願できるよう指導を依頼するとともに、共通テストの実施についてのご協力をお願いしています。
- 出願手続きや受験上の留意点等を十分に理解してもらえるようにするため、解説資料等を提供の上、高等学校等向けに説明協議会を実施し周知しています。また、SNS等を用いた発信も行っています。

出願の受理、試験場の指定、受験票の発行
約49万人の出願を処理し、実施に向けた準備を滞りなく進めています。
出願の受理(Web出願)
出願の受理やシステム上の処理などを行います。
試験場の指定
- 共通テストの試験場の設定は、原則として都道府県ごとに組織される、利用大学間での連絡会議において協議されます。
- センターは、確定した志願者情報をもとに、各志願者の試験場を指定します。
- 指定にあたっては、志願者数の分布や、試験場の収容数やトイレ等の設備、一部教科についての受験する科目数の組合せ等、様々な要素を考慮します。
- 原則、高等学校等(通信制課程を除く。)に在籍している卒業見込みの志願者は高等学校等の所在地をもとに、それ以外の出願資格の者は出願内容を登録した際の現住所をもとに、試験場を指定します。

受験票の発行
- 12月上旬頃までに、受験票を発行します。受験票には、試験場や登録教科等が表示されます。
- 志願者は、共通テスト出願サイトのマイページから受験票をダウンロードして印刷し、試験当日に持参する必要があります。
- 共通テストの受験に当たっての注意事項等が記載された「受験上の注意」を公表します。
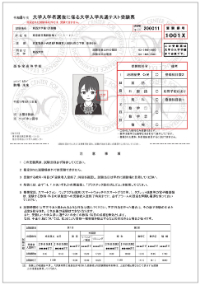 受験票の見本
受験票の見本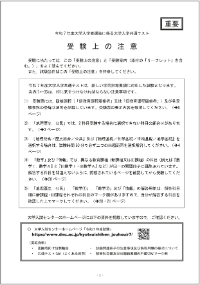 受験上の注意の表紙
受験上の注意の表紙
(令和7年度共通テスト)
受験上の配慮事項の決定等
病気・負傷や障害等のために、受験に際して配慮を希望する志願者に対し、個々の症状や状態等に応じた受験上の配慮を行っています。
受験上の配慮について
- 受験上の配慮については、障害等の種類や程度にかかわらず、必要な配慮事項を申請することができます。
- 志願者から提出された申請書類について不明な点等がある場合は、センターから志願者に連絡の上、確認や相談を行います。
- 申請のあった配慮事項については、センターに設置する、医師や特別支援教育の専門家で構成する会議体において、個々の症状や状態等を総合的に判断の上、審査を行い、その結果を志願者に通知しています。
- 許可された配慮事項については、必要に応じて志願者や試験場大学と事前に打ち合わせを行います。
- 志願者専用の電話を設け、年間を通して個別相談にも対応しています。
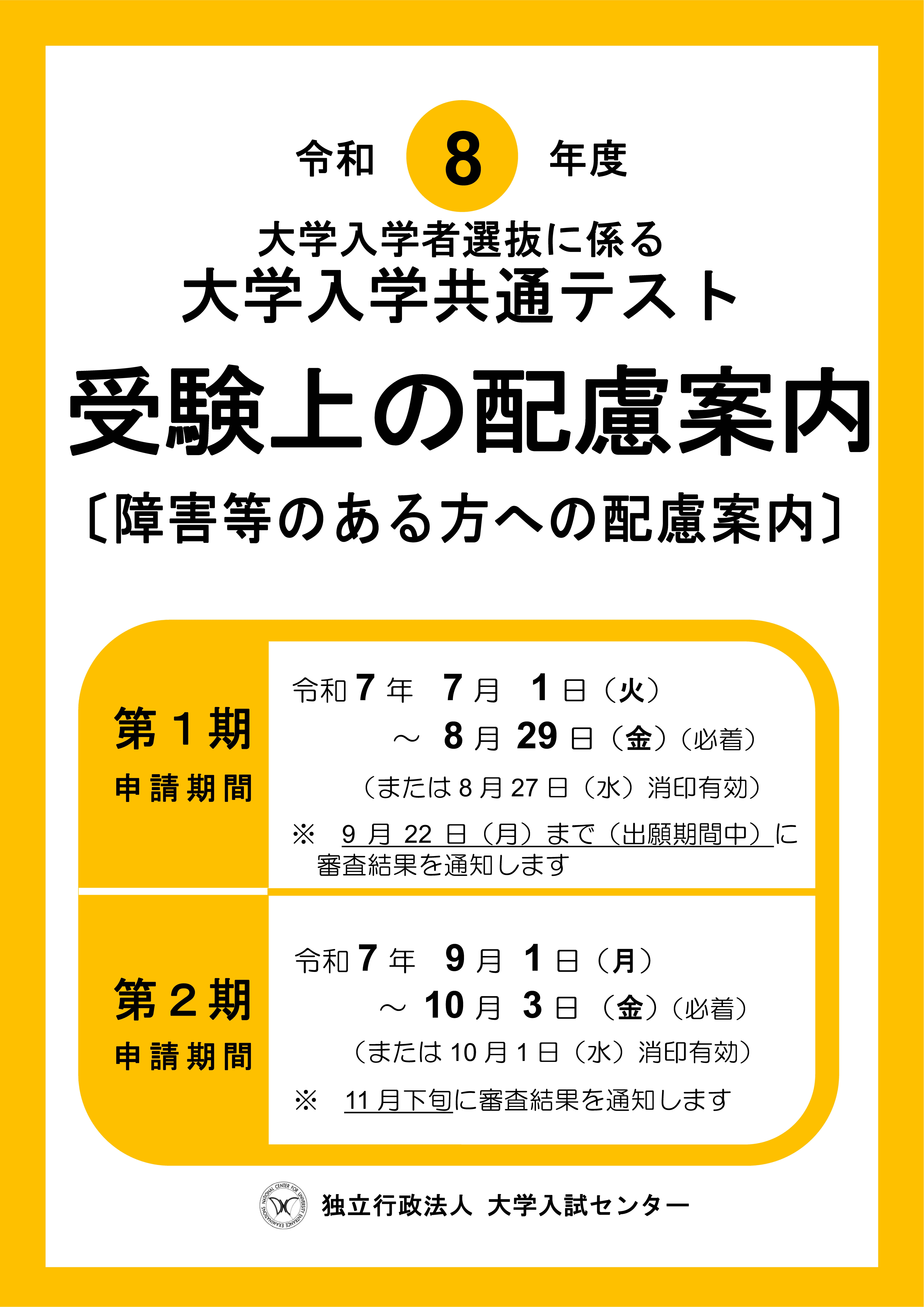 受験上の配慮案内の表紙
受験上の配慮案内の表紙(令和8年度共通テスト)
主な配慮事項(例)
| 配慮の種別 | 主な配慮事項(例) |
|---|---|
| 解答方法や試験時間に関する配慮 | 点字解答、文字解答、チェック解答、代筆解答、試験時間の延長(1.3倍、1.5倍) |
| 試験室や座席に関する配慮 | 1階又はエレベーターが利用可能な試験室で受験、トイレに近い試験室で受験、座席の指定(前列に指定、出入口に近いところに指定、窓側の明るい座席を指定など)、別室の設定 |
| 持参して使用するものに関する配慮 | 拡大鏡等の持参使用、補聴器又は人工内耳の装用、車椅子の持参使用、杖の持参使用、特製机・椅子の持参使用 |
| その他の配慮 | 拡大文字問題冊子(文字サイズ14ポイント、22ポイント)の配付、特製机・椅子の試験場側での準備、手話通訳士等の配置、注意事項等の文書による伝達、リスニングの免除、リスニングにおける音声聴取方法の変更、試験場への乗用車での入構 |
各種マニュアル等の整備、試験実施業務の周知徹底
共通テストの公平かつ円滑な実施のためのマニュアル等の策定・周知を行っています。
各種マニュアル等の整備
- 共通テストは、同一の期日に同一の試験問題により、全国約660の試験場において実施する全国規模の試験です。各試験場において公平かつ円滑に試験が進められるよう、「実施要領」や「監督要領」等の、統一的な基準を示す各種マニュアルを整備しています。
- 各種マニュアルは、過年度試験の実施結果や、各利用大学からの意見・要望などを踏まえて、毎年見直しを行っています。

試験実施業務の周知徹底
各利用大学に対して、留意点や、前年度からの変更点等を分かりやすく解説した説明資料や解説ビデオを提供の上、入試担当者連絡協議会を実施し試験実施業務の具体的内容について周知徹底を行っています。 また、監督者等へ対し、監督業務及び担当業務を周知徹底するための監督者等説明会を開催するよう要請しています。
試験問題の作成・点検
良質な問題の作成に取り組んでいます。
共通テストは、大学入学志願者が大学で学ぶために必要な能力を有しているかを各大学が把握することができるよう、高等学校の段階における学習の達成の程度を判定することを目的としており、 良質な問題を作成することはセンターの重要な使命です。
センターでは、毎年の問題作成や点検を慎重に行うとともに、試験終了後には問題に関する外部評価、自己点検・評価を行い、良質な問題の作成に取り組んでいます。
センターでは、毎年の問題作成や点検を慎重に行うとともに、試験終了後には問題に関する外部評価、自己点検・評価を行い、良質な問題の作成に取り組んでいます。
約2年間にわたる問題作成と点検の体制
- センターでは、試験実施の約2年前に「問題作成方針」を策定し、公表します。この問題作成方針に基づいて、問題作成や点検が行われています。
- 各分野の専門性を有する国公私立大学の教員等、700人以上が問題作成や点検に携わっています。
- 情報漏洩防止の観点から、問題作成や点検はセンターの施設内で行われており、問題作成委員は、年間約15回、延べ50日程度(1回あたり3~5日程度)センターに来訪し、問題作成にあたります。
- また、点検委員は、問題の正確性やクオリティを高めるため、学術的な観点や、問題作成方針との整合性、難易度や出題範囲等の妥当性の観点など、様々な観点から点検を行うとともに、科目間の内容の重複等についても横断的・総合的に点検しています。
- 問題作成委員は、点検委員からの意見を踏まえて更に問題に修正を加えます。問題作成は、「作成(修正)」と「点検」のサイクルを複数回繰り返しながら、十分な議論を尽くし、慎重に行われています。
- なお、委員の氏名をはじめとする問題作成に関わる情報は厳重に管理しており、各委員は、職務を遂行する上で知ることのできた情報に関し、その任を退いた後も秘匿する必要があります。ただし、各人が委員に就任していた事実については、各人の離任後一定期間を経た後に、官報を通して公表しています。
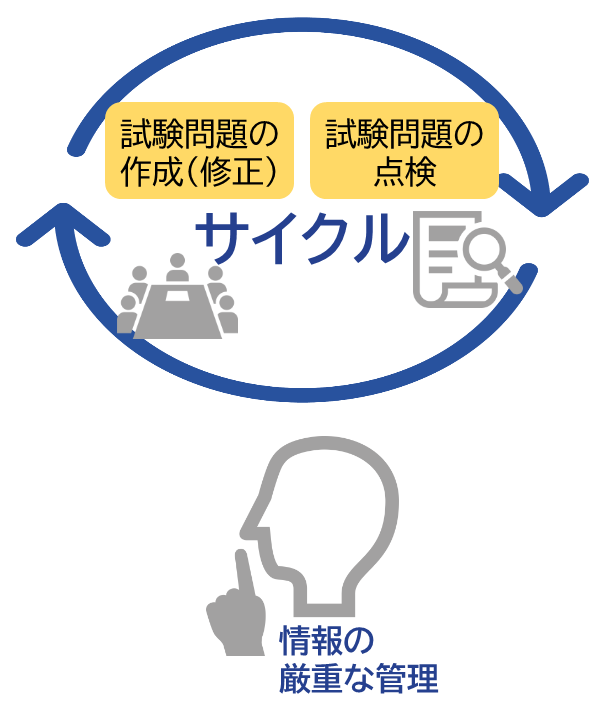
試験問題等の印刷・輸送
印刷・輸送における安全で確実な輸送体制の確保及び秘密の保持を徹底しています。



- 試験問題冊子や解答用紙等は、堅固なセキュリティを確保の上で印刷を行った後、安全で確実な輸送体制のもと、センターから専用コンテナで試験場の大学に輸送しています。
- 大学に対して、秘密保持など輸送時の留意点を周知徹底するほか、万が一のトラブル発生時でも迅速に対応できるよう緊急時の体制を整えています。
共通テスト実施当日の業務
共通テストの公平かつ円滑な実施のため、各実施大学と緊密な連携体制を敷いています。
- 共通テスト当日は、約660の試験会場、約1万の試験室(本試験)で連絡調整を行いながら試験を実施します。
- 約49万人規模の試験を適切に実施するため、大学入試センターが作成した各種マニュアルに基づき、全国で数多くの大学教職員が試験の運営(試験本部作業、試験監督、受付、警備等)を担当します。
- センターと各大学との連絡交信には、専用の電話・PCを準備し、緊密な連携体制を敷いています。
- 受験上の配慮については、必要に応じて受験者や試験場大学と事前に打ち合わせを行った上で試験を実施しています。
共通テスト実施後の業務(答案の採点、成績開示など)
答案の採点・集計
正確な採点のために万全を期しています。
- 受験者の答案等は、すべてセンターに返送されます。返送される答案枚数はおよそ300万枚です。
- 答案は、OMR(光学式マーク読取装置)を用いて、約4日間かけて読み取ります。
試験成績の各大学への提供
- 共通テスト利用大学は、志願者の「成績請求情報」(注)に基づき、センターに成績を請求します。なお、志願者は、各大学の大学入学共通テストを利用した選抜区分に出願する場合、「成績請求情報」を志望大学へ提供するための手続が必要です。
(注)「成績請求情報」とは、各大学が大学入試センターに志願者の大学入学共通テストの成績を請求するための情報です。 - センターは、利用大学の請求に基づき、共通テストの成績を提供しています。
- 令和7年度共通テストでは、利用大学に対して、のべ1,638,158件の成績を提供しました。提供件数の内訳は表のとおりです。
| 種別 | 成績提供件数(件) |
|---|---|
| 国立大学 | 324,301 |
| 公立大学 | 138,156 |
| 私立大学 | 1,172,418 |
| 短期大学 | 2,948 |
| 公立専門職大学 | 212 |
| 私立専門職大学 | 123 |
| 合計 | 1,638,158 |
試験成績の開示
出願時に成績の閲覧を希望した受験者は、試験終了後の4月以降の一定期間、共通テスト出願サイトのマイページから成績を閲覧できます。
試験問題の外部評価と自己点検・評価
- 問題の質を高めるため、各年の試験終了後、問題ごとの正答率などの詳細な分析を基に、高等学校等教員・教育研究団体による外部評価と問題作成者による自己点検・評価を実施し、その評価結果を次年度以降の問題作成に活用しています。
- 評価結果については、各教科の正答率や得点分布などとともに問題評価・分析委員会報告書として公表しています。