得点調整の研究
令和7年3月26日
(取材日:令和7年2月14日)
(取材日:令和7年2月14日)
入試の公平性をめざして―新しい得点調整とその実装―
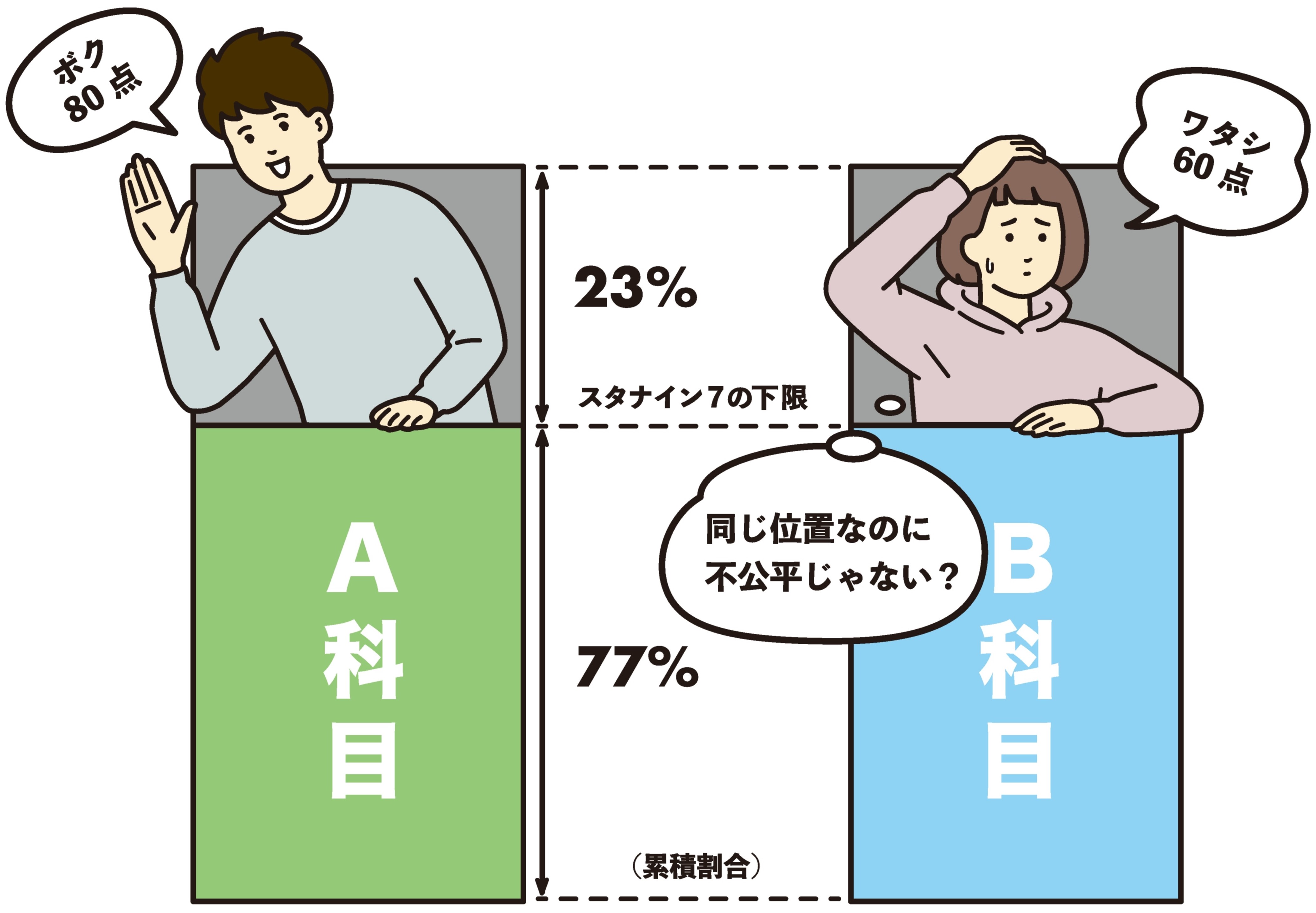
大学入試センター試験から、大学入学共通テストへ。我が国を代表する大規模な一斉試験も進化を続けている。試験の時間割や出題される教科・科目が変わっていくなか、令和7年度大学入学共通テストから「得点調整」の実施条件や調整の仕組みの改善を行った。試験の公平性をさらに高い水準で維持するために、これまで特定の科目間で、平均点に著しい差が生じた場合に実施してきたが、今後は平均点差に加え、段階表示の得点差も調整の条件となった。新たな得点調整の詳しい仕組み、さらに変更に至った経緯や通底する公平性の理念について、得点調整の研究を牽引してきた、研究開発部の部長である石岡恒憲教授と、荘島宏二郎教授に話を聞いた。
(取材・文 丸茂健一/minimal)
(取材・文 丸茂健一/minimal)
INDEX
得点調整とは何か?
得点調整とは、同じ教科の中での選択科目による有利不利を緩和し、試験の公平性を保つために、あらかじめ定めた一定の条件のもと、一部の教科の科目間で得点の補正を行う仕組みを指す。過去の大学入試センター試験(以下、センター試験)、大学入学共通テスト(以下、共通テスト)でも、特定の科目間で試験問題の難易差に起因する大幅な得点差が生じた場合に実施されてきた。研究開発部長の石岡恒憲教授はこう語る。
「どの科目を選んでも等しく実力が評価される試験が理想です。そのため、当センターでも試験問題の作成の段階で、著しい平均点差が生じないよう、できる限りの努力をしています。しかし、幅広い受験者に向けて、たくさんの科目を準備し、50万人近くが受験する共通テストにおいて、平均点を一定に保つのは極めて困難です。そこで、対象となる選択科目間において一定の平均点差が開いた場合には、得点調整を行うこととしています。」
現在の得点調整方法は、平成10年度試験以降の方法として確立された「分位点差縮小法*」が基軸となっている。
平成10年度試験から令和6年度試験までの間の得点調整方法
(以下、受験案内を要約)- 該当する教科内の科目間において、原則として20点以上の平均点差が生じ、これが試験問題の難易差に基づくものと認められる場合に得点調整を行う。
- 分位点差縮小法*という方式を用いる。
- 得点調整に当たっては、受験者間での公平性の観点から、平均点差の全てを調整するのではなく、調整後も平均点差が15点となるようにする。
- 1万人未満の科目は得点調整の対象としない。
*分位点差縮小法:
得点調整の対象となる科目のうち、最も平均点の高い科目と最も平均点の低い科目の得点の累積分布を比較し、図の縦軸の受験者数の累積割合(%)が等しい点(等分位点)の差(分位点差)を、一定の比率で縮小する方式
得点調整が最初に行われたのは、共通第1次学力試験の最終年である平成元年度試験まで遡る。「理科」の科目間に著しい得点差が生じ、上記とは異なる方法で得点調整を行った。その後、調整は行われてこなかったものの、科目数の増加やアラカルト方式の導入も踏まえ、現在にも繋がる分位点差縮小法が確立された。詳しく見ていこう。
きっかけは平成9年度センター試験。既卒生のために用意した旧課程科目が難しく、大きな点差が開いたにもかかわらず、調整を行わなかったために大きな批判を受けた。このため、平成9年にセンターに外部有識者を集めた検討会議を組織し、研究開発部の教員とともに検討を重ねて開発した。以降、平成10年度試験より、この調整方法が適用されてきた。
きっかけは平成9年度センター試験。既卒生のために用意した旧課程科目が難しく、大きな点差が開いたにもかかわらず、調整を行わなかったために大きな批判を受けた。このため、平成9年にセンターに外部有識者を集めた検討会議を組織し、研究開発部の教員とともに検討を重ねて開発した。以降、平成10年度試験より、この調整方法が適用されてきた。
石岡恒憲教授は続ける。
「得点調整を実施することにより、新たな不公平感が生じる可能性も否定できず、調整後できるだけ受験者全体の不公平感が少なくなるような方式を模索しました。その結果、得点調整を実施する場合は、受験者の心理に配慮し、素点は下げないことを原則と掲げました。」
「得点調整を実施することにより、新たな不公平感が生じる可能性も否定できず、調整後できるだけ受験者全体の不公平感が少なくなるような方式を模索しました。その結果、得点調整を実施する場合は、受験者の心理に配慮し、素点は下げないことを原則と掲げました。」
実際に行われた調整:分位点差縮小法
では深入りして、分位点差縮小法について、実際に行われた得点調整を例に、見てみよう。平成10年度センター試験の地理歴史において、「日本史B」と「地理B」の平均点の間に約21点の差があった。平成10年1月23日(試験終了後5日目)、大学入試センターは、この点差が「問題の難易差で生じた」と認め、地理歴史の得点調整の実施を発表した。そして、翌日の朝刊には、分位点差縮小法に基づく「得点換算表」が掲載された。
平均点差約21点差を15点に縮めたため、点数の低い「日本史B」の平均は約6点の上昇であるが、全員に対して一律に6点を加算するのではなく、0点は0点に、100点は100点のまま、0点や満点の近傍の得点はほとんど変化しないのに対し、中間の43点から57点のあたりでは(平均点差を超える)7点の嵩上げがされた。「分位点差縮小法」とは、このように非線形な得点調整の方法である。
分位点差縮小法に基づく得点調整は、その後、平成27年度(理科②)に、また共通テストになってから令和3年度(公民、理科②)と令和5年度(理科②)の計3年、4教科で実施された。大きな混乱もなく、この方法は社会、受験生にも受け入れられていると判断していいだろう。これまでの経緯を現場で見てきた荘島宏二郎教授は次のように語る。
「簡単に申し上げると、『平均点』を基準とする得点調整を行ってきました。
具体的には、科目間で20点以上の平均点差が出て、問題の難易差に基づくものだと認められた場合、平均点差を15点に縮める措置です。
できる限り多くの受験者の公平性が保たれ、受験者にとって分かりやすく、さらに調整の作業を、短期間で適切に遂行できるものとして、定着してきた方法です。」
具体的には、科目間で20点以上の平均点差が出て、問題の難易差に基づくものだと認められた場合、平均点差を15点に縮める措置です。
できる限り多くの受験者の公平性が保たれ、受験者にとって分かりやすく、さらに調整の作業を、短期間で適切に遂行できるものとして、定着してきた方法です。」
令和7年度試験から用いられる新しい得点調整法
大学入学共通テストの導入と、より進化する得点調整-
周知のとおり、令和3年度試験よりセンター試験から共通テストへと変わった。この変更に伴って、受験者の成績を、それまでの素点に加え、段階表示(分位点による区分法。1から9の9段階に換算する方式=スタナイン)についても、大学の多様なニーズに応えるべく提供することになった。このように、教育改革に伴い共通テストも変化、進化が進む一方で、得点調整についても、より公平性を高めるものにできないか。研究開発部でも研究を積み上げていた。その末に・・・
「さらに公平な試験運用を模索するなかで、『区分点差』という新たな基準を採用した得点調整の方法を導入するという結論に至りました。」(前出:荘島教授)
令和7年度からの新しい得点調整法の実装に至るまでの経緯を、詳しく紹介していこう。
それまでは-
これまでの得点調整は、対象科目間の平均点差に着目し、①対象科目間で平均点差が20点以上開き、それが試験問題の難易差によるものである場合に、②平均点差が15点差となるよう調整を行うこととしてきた。この方法は、受験者や関係者に広く定着してきた。しかし(問題点)-
「平均点」を基準とした調整だけでは、十分な調整を行うことが難しい場合が生じうる。科目の得点分布の形が大きく異なる場合には、平均点差が一定の範囲内に収まっても、成績の段階表示の同段階間で大きな得点差が生じる可能性がある。(下の図1を参照)特に令和7年度試験は、平成30年告示学習指導要領に対応して出題教科・科目の構成が変わるとともに、経過措置科目もあるため、上記のような状況が起こりやすくなる。(下の図2を参照)
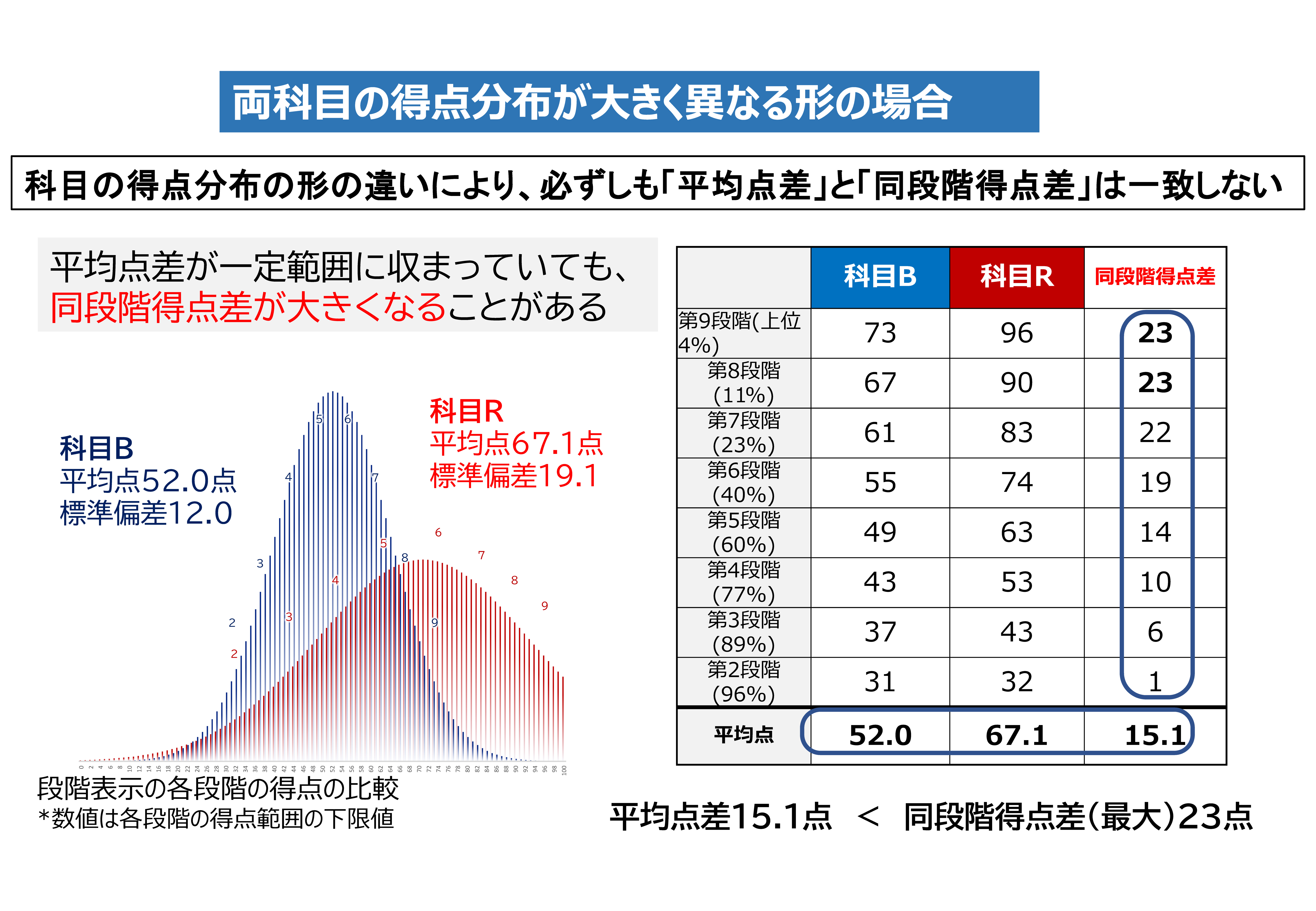 図1 「平均点差」と「段階表⽰の区分点差」の関係
図1 「平均点差」と「段階表⽰の区分点差」の関係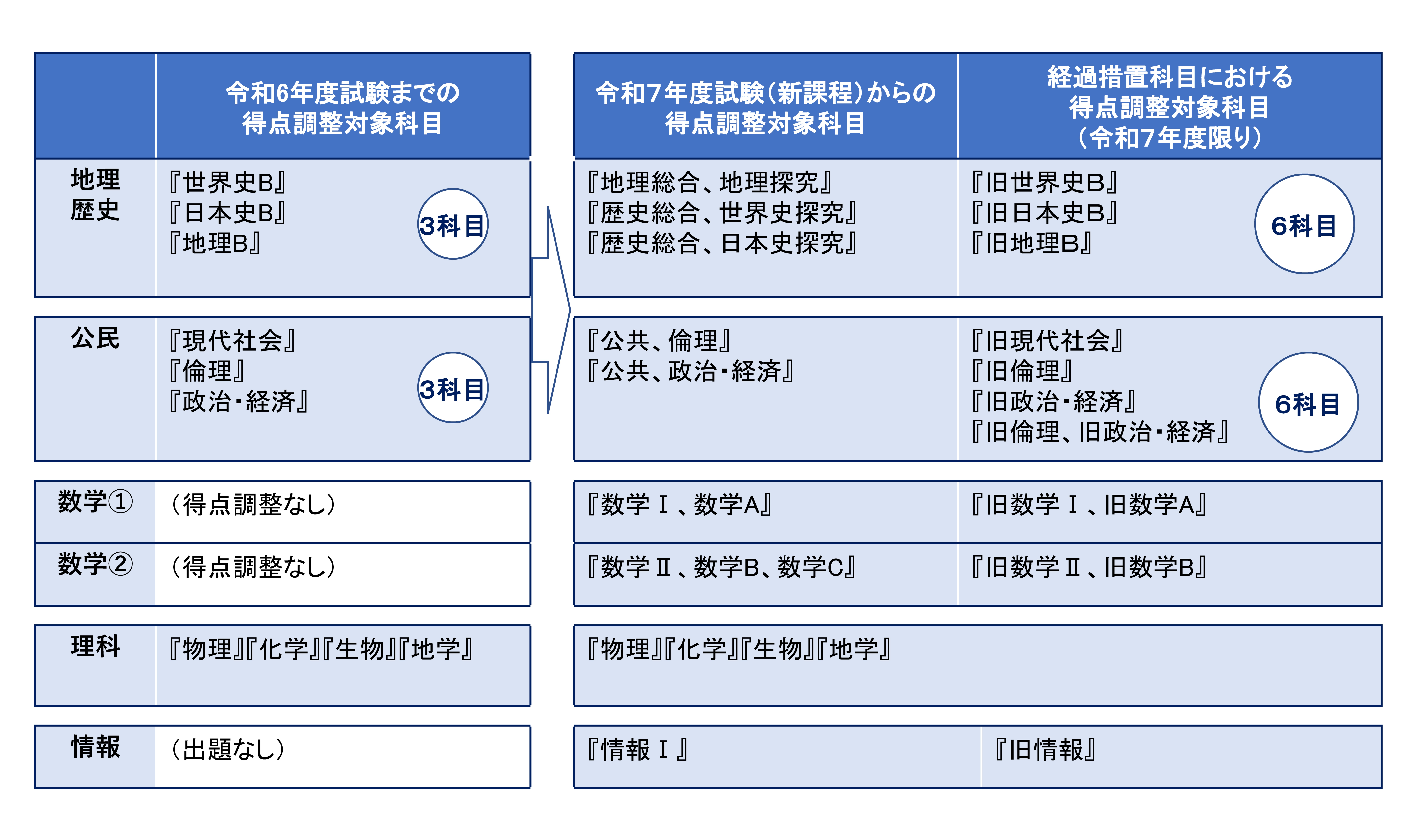 図2 令和7年度試験における得点調整の対象科目
図2 令和7年度試験における得点調整の対象科目解決策-
平均点差を一定範囲内に収まるようにするという従来の調整方法を生かしつつ、段階表示の同段階間での得点差についても一定の範囲に収まるような実施条件・方法とすることが望ましい。具体的には、従来の「20点以上の平均点差が生じた場合」に加え、「15点以上の平均点差が生じ、かつ、段階表示の区分点差が20点以上生じた場合」も得点調整の対象とし、調整の方法は、「区分点差が最大15点となるよう調整する」こと。
(令和4年11月16日独立行政法人大学入試センター「大学入学共通テスト得点調整の実施条件・方法の改善についての提言」(得点調整検討部会審議のまとめ)より)
大学入試センターでは、主に研究開発部や得点調整検討部会において、令和7年度試験から出題教科・科目の構成や内容等が変わることを機に、得点調整の在り方についても議論を進めてきた。このような経緯を踏み、上記の解決策の提言を実装する形で、今回の新しい得点調整法、つまり区分点差を調整の条件に加えることになったのだ。
得点分布の形によっては、平均点差を一定の範囲に収めるよう調整しても、段階表示の同段階間で大きな得点差が残ることがある。実際の大学での合否判定における影響を考慮するには、さらに段階表示の同段階間での得点差についても一定の範囲に収まるような方法が望まれる。このニーズにも応えられるものとして導入した。
得点分布の形によっては、平均点差を一定の範囲に収めるよう調整しても、段階表示の同段階間で大きな得点差が残ることがある。実際の大学での合否判定における影響を考慮するには、さらに段階表示の同段階間での得点差についても一定の範囲に収まるような方法が望まれる。このニーズにも応えられるものとして導入した。
令和7年度試験からの得点調整方法
(以下、受験案内を要約)
-得点調整の実施条件-
得点調整の対象となった各科目間で、次のいずれかが生じ、これが試験問題の難易差に基づくものと認められる場合には、得点調整を行う。
ア)20点以上の平均点差が生じた場合
イ)15点以上の平均点差が生じ、かつ、段階表示の区分点差(注)が20点以上生じた場合
(注)ここでいう区分点差とは、各科目の成績の段階表示(スタナイン)の各段階の境目となる、上から4%、11%、23%、40%、60%、77%、89%、96%の分位点(得点)の差を指します。
従前はア)のみであったが、今回、イ)も追加された。詳細は下図の通り。
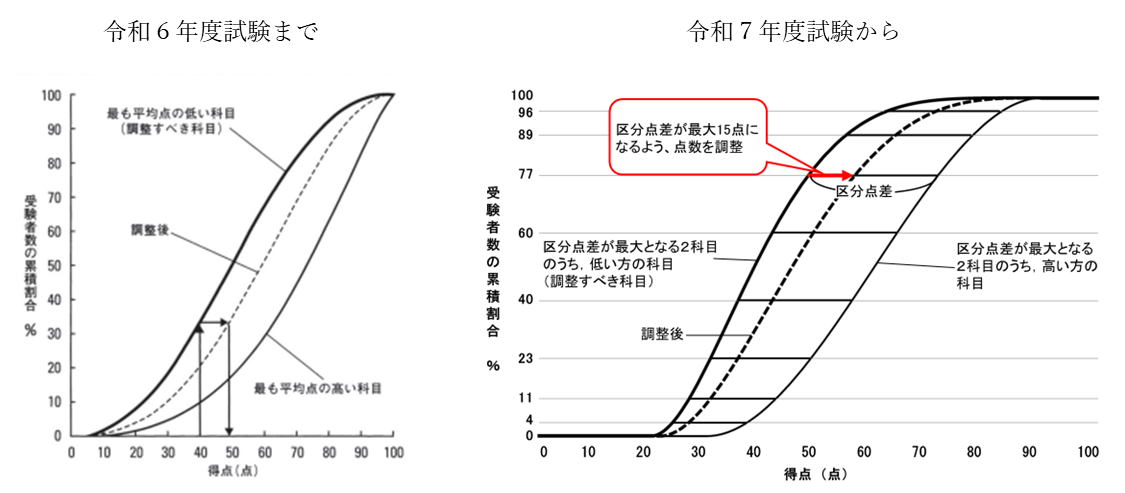 令和7年度試験からの「8つの区分値を用いた分位点差縮小法」
令和7年度試験からの「8つの区分値を用いた分位点差縮小法」「今回の改訂の要諦は『なぜ平均点差のみを目安に得点調整するのか』への回答でもあります。共通テストの受験者には高得点者もいるし、平均的な者もいるし、そうでない人もいる。受験者が多様化している中、平均点差のみに着目するのではなく、様々な段階での得点差を考慮していることに今回の改訂の特徴があります。」(前出:石岡教授)
終わりに:得点調整の研究を積み重ねてきた、それぞれの想い
これまでの長年に亘る得点調整の研究の軌跡を踏まえ、今後も公平な試験運用をめざすに当たって、最後に、先生それぞれに想いや決意を聞いた。得点調整にも新たな技術革新が必要-
センター試験以降、アラカルト方式と呼ばれ、受験者が必要とする科目のみを選択・受験できるようになっている。ポイントは、全受験者が全科目を受験しているわけではないところにある。「近年は、このようなデータを積極的に取り扱う新しい手法も考案され広く利用されつつあります。研究開発部でも、これら技術的進展を踏まえ、さまざまな方法を模索、検討しています。最先端の機械学習を用いた方法も検討しました。これらの新しい複数の手法を用い相互に検証することで、科目間の得点差が試験問題の難易差によるものと認められるかの判断をします。
一方で、ここまでの検証から実装までも含め、運用には、チーム一体となってこの精緻な作業に取り組むことが必要です。入念に、試験の前に複数のプログラムによる相互確認やシミュレーションを行ったり、様々なチェックを重ねたり。出題形式の変更によるプログラムの更新も必要です。試験後は、全国からのマークシート300万枚以上の生きた答案データを処理したり。
毎年、使命感を持って一丸となって取り組んでいます。」(前出:荘島教授)
一方で、ここまでの検証から実装までも含め、運用には、チーム一体となってこの精緻な作業に取り組むことが必要です。入念に、試験の前に複数のプログラムによる相互確認やシミュレーションを行ったり、様々なチェックを重ねたり。出題形式の変更によるプログラムの更新も必要です。試験後は、全国からのマークシート300万枚以上の生きた答案データを処理したり。
毎年、使命感を持って一丸となって取り組んでいます。」(前出:荘島教授)
宮澤芳光 研究開発部 准教授・・・主に成績データ構造の変化に対応して、適切なデータを取得する作業を担当
成績、点数の文化の中で-
「これまで採用されてきた分位点差縮小法は、0点は0点に、100点は100点のままにしておくべき、という素点を大切にした考えを実装した方法です。一方で、テストの得点表示の仕方は、例えば、大規模な英語の試験で有名なTOEFLⓇのように、偏差値のような標準化得点もある。しかし、共通テスト(過去にはセンター試験)は受験者の得点を素点で提供するという前提のもとに、得点調整の方法が検討されてきました。標準化得点であれば得点調整は不要ですが、日本の大学入試には、素点主義の文化があります。併せて共通テストの成績は、大学に提供し、その大学での入試も含めて最終的に合否を判定する。という構図もあります。これらの背景も含め、今後も、日本の試験文化を踏まえ大切にしつつ、広い視点を持って、より良い方法を模索していきたいと考えています。」(前出:石岡教授)石岡教授、荘島教授、専門の検討部会等をはじめ、様々なスタッフの、これまでの経験や知見が集積された「得点調整」。
多くの人が通り過ぎる試験には、“公平性”が存在する。誰もが望みつつも、一方では掴みづらい、試験における公平性の理想への、大学入試センターの追求は続く。
多くの人が通り過ぎる試験には、“公平性”が存在する。誰もが望みつつも、一方では掴みづらい、試験における公平性の理想への、大学入試センターの追求は続く。
引用:図1・2「⼤学⼊学共通テスト得点調整の実施条件・⽅法の改善についての提⾔」(得点調整検討部会審議のまとめ)別紙「得点調整の実施条件・⽅法に関する得点調整検討部会の考え⽅」に関する補⾜説明資料(令和4年11月16 日独立行政法人大学入試センター「大学入学共通テスト得点調整の実施条件・方法の改善についての提言」(得点調整検討部会審議のまとめ)の公表及び意見募集について より抜粋)